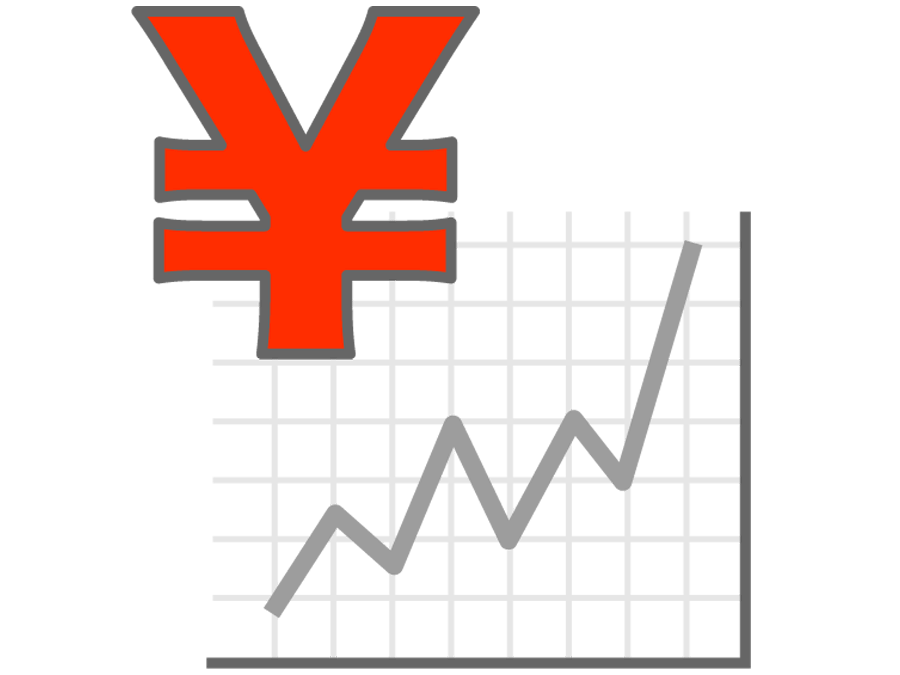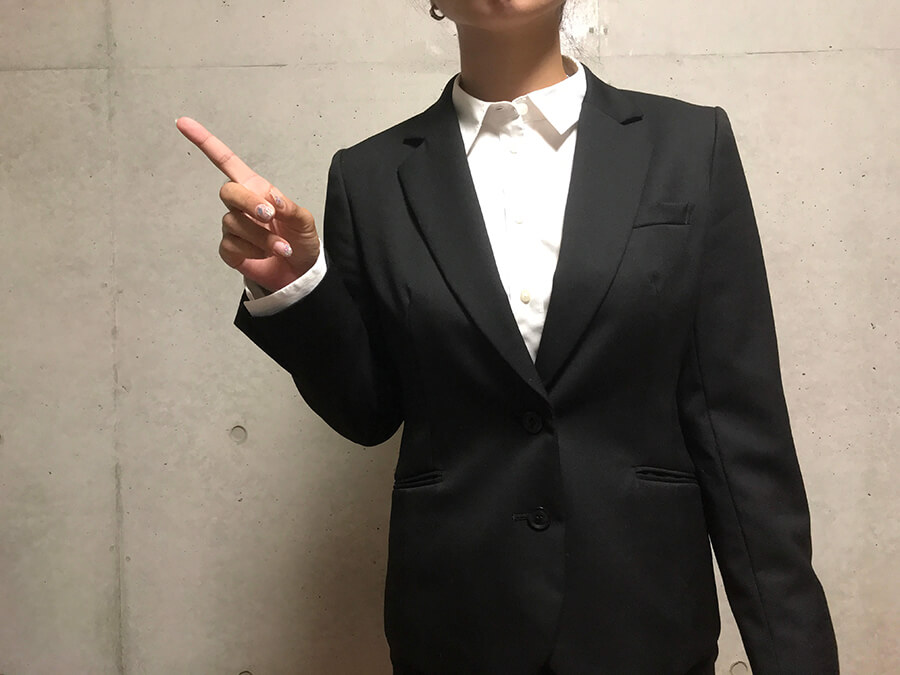一般NISA・つみたてNISAのおさらい
2014年に開始したNISA(少額投資非課税制度)は、満20歳以上なら誰でも開設できる投資で、非課税枠が年間120万円となります。
つまり、毎年120万円までなら投資で儲けた利益が非課税となる制度です。
期間は5年間なので、5年で最大600万円まで投資で得た利益が非課税対象になります。
投資は株式と投資信託から選べるようになっており、自由度が高いことが特徴です。
税制改正により一般NISAは終了となる予定でしたが、新NISAが登場したことで2028年まで延長されました。
つみたてNISAは長期的な資産形成支援のために登場したもので、非課税枠は一般NISAの3分の1の年間40万円ですが、その期間が最長20年となっています。
つまり、合計800万円まで利益が非課税になるという仕組みで、指定の投資信託に限られているのが特徴です。
このつみたてNISAも2042年まで延長となっています。
2024年「新NISA」スタート!
一般NISAの仕組みをベースに新しく登場したのが新NISAです。
新NISAも一般NISAと同様に5年間の非課税期間というのは変わりませんが、この非課税枠の構造が大きく変更となっています。
まず、新NISAの非課税枠は年間122万円となり、さらに2階建てシステムになったことが大きな特徴です。
1階は20万円、2階は102万円という内訳になっており、さらに1階部分では投資対象は投資信託限定となるため株式を購入できなくなっています。
これはつみたてNISAに通じる仕組みであり、長期的な資産形成を目的としたシステムです。
1階部分の20万円の非課税枠を使い切ってはじめて、2階部分の102万円の非課税枠を利用できるようになります。
2階部分は一般NISAと同じで株や投資信託から好きに購入でき、1階2階を合わせて5年間で合計610万円、一般NISAより10万円多い非課税枠で投資が可能です。
この新NISAは、2024年(令和6年)から実施されます。
新NISAになってどう変わるの?
一般NISAに比べると、新NISAは若干複雑な仕組みに変化しています。
1階部分がつみたてNISAのシステムと同様になっていることから、個人の投資家に長期的かつ安定した運用を促していることが伺えます。
株式は短期でもリターンを得ることができるため、長期的な投資よりデイトレードのような短期的投資に利用されるケースも多かったのでしょう。
そこで1階の非課税枠20万円を長期投資向けの投資信託に絞ることで、個人投資家の安定した運用を図っているのです。
ではなぜつみたてNISAに統一せずに新NISA制度を作ったのか、それは投資意欲を失わせない目的があります。
これから長期的かつ安定した投資を始めたいという方にふさわしい投資方法となっています。