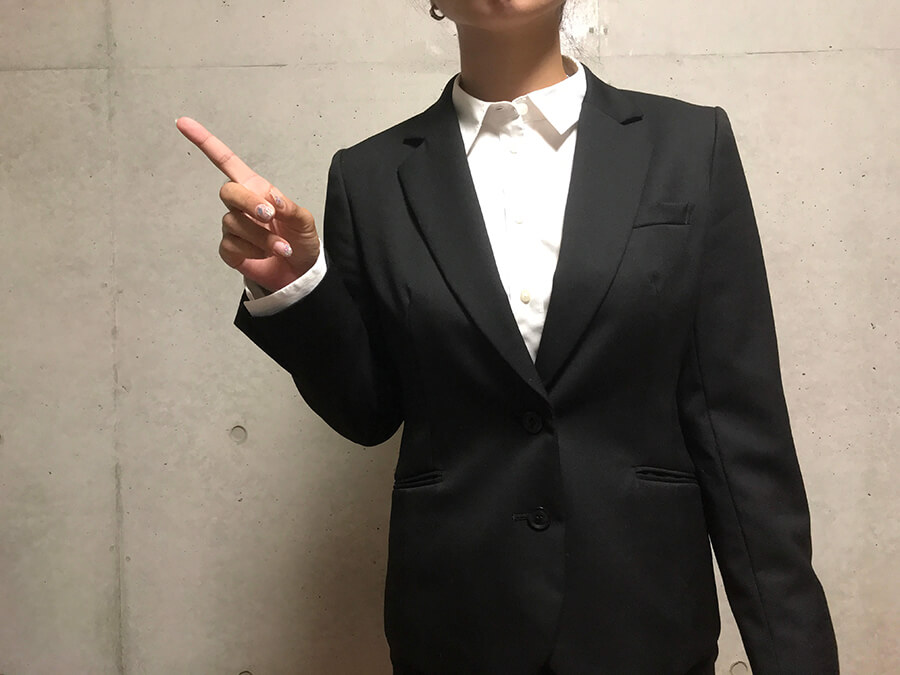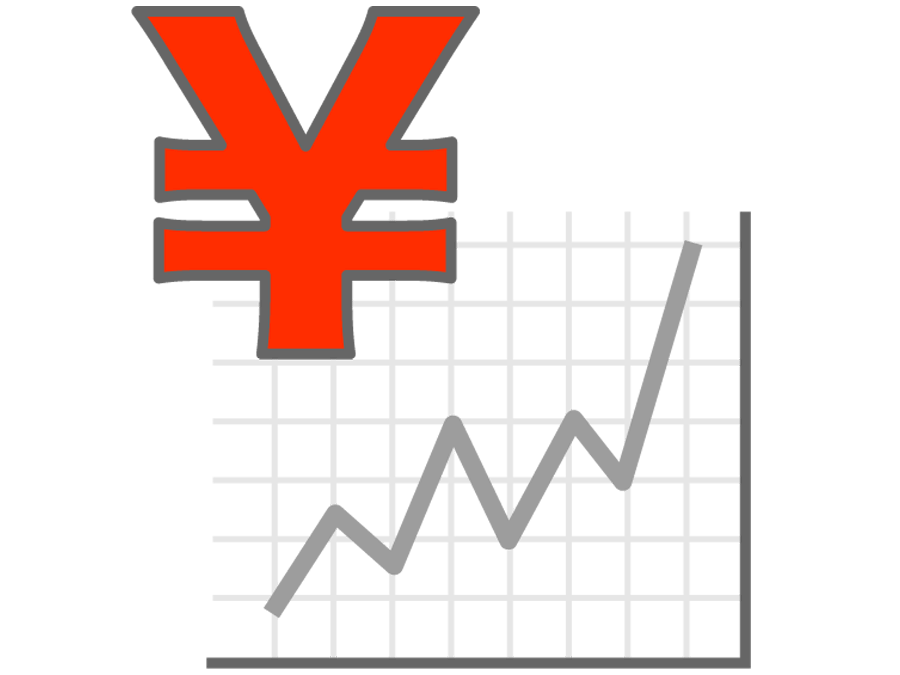「高額療養費制度」で医療費負担を減らそう
高額療養費制度を利用したことはありますか?
名前を聞いたことはあるけど、特に大きな病気をしたこともないし関係ないだろうと思っていても、いざ大病をしたときに制度を知らないと戻ってくる医療費も戻ってきません。
万が一に備えて、高額な医療費負担を軽減できる「高額療養費制度」についてきちんと理解しておきましょう。
高額療養費制度とは、医療機関で診察や治療のために使った医療費が一定額、つまり自己負担限度額を超えた場合に、申請することで払い戻される公的健康保険制度のことです。
自己負担限度額は所得によって5つに分けられており、69歳以下の方で住民税非課税者は35,400円、年収370万円の方は57,600円、年収370万~770万円の方は{80,100円+(医療費-267,000円)×1%}で割り出されます。
例えば、世帯主である夫(50歳)・年収600万円として、6月から7月にかけてA病院で入院をして6月は3万円、7月に15万円を一部負担、妻(45歳)は7月にB病院で外来にかかり6万円を一部負担したとします。
21,000円以上の一部負担金を月ごとに合算すると、6月は3万円、7月は21万円で、計算式の「医療費」は10割分となるため6月は10万円、7月は70万円です。
6月分は30,000-{80,100+(-167,000)×1%}となり-48,430円、7月分は210,000-{80,100+433,000×1%}となり125,570円となります。
つまり、6月は自己負担限度額より下回るため該当せず、7月は高額医療費に該当するため125,570円が戻ってくるという計算です。
高額療養費制度を利用するには
高額療養費を申請するには、加入している公的健康保険に支給申請書を提出しなければいけません。
国民健康保険に加入している場合、高額医療費制度に該当するケースにおいて保険者の市区町村から申請書が送付されます。
加入する保険によっては申請不要なものもあり、医療機関の利用の際に自動で計算され、対象であれば口座へ支給額が振り込まれます。
注意点としては、高額医療費の申請には時効が設定されているという点です。
また医療機関に支払った後でしか申請できないため、早めに支払いを済ませて速やかに申請しておきましょう。
「限度額適用認定証」を受け取っておこう
高額療養費制度は基本的に先に医療費を支払い、後から申請して払い戻される仕組みになっています。
先に自腹で全額負担するのが厳しいという方は、「限度額適用認定証」を受け取っておくことをおすすめします。
この認定証があれば、医療機関を利用する際に窓口で提示すれば、支払い時にすでに高額療養費制度が適応された自己負担限度額までの額となるため安心です。